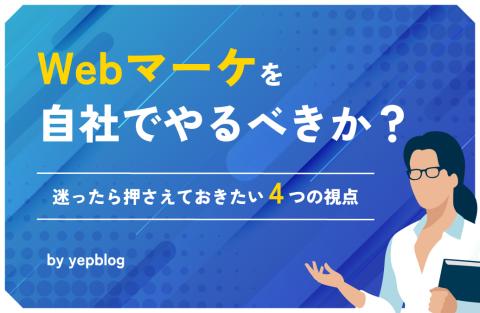
目次
はじめに:Webマーケティング、自社でやるべき?外注すべき?この悩みを解決する4つの視点
Webマーケティングは、Webサイトなどを中心に行われるマーケティング手法です。インターネットの普及とEC市場の拡大に伴い、多くの企業にとって必要不可欠となっています。
Webマーケティングの最大のメリットは、施策の効果を数値化しやすく、データに基づいて改善を行いやすい点です。自社の商品やサービスを効果的にアピールし、潜在顧客を集客するために非常に有効です。
しかし、「Webマーケティングを自社で行うべきか、それとも専門業者に外注すべきか?」という悩みをお持ちの担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、この重要な問いに対する答えを見つけるために、以下の4つの視点からWebマーケティングの内製化について掘り下げていきます。
-
なぜ今、内製化を検討する企業が増えているのか?
-
自社で行うことのメリット・デメリット
-
内製化の具体的なステップ
-
内製化に向いている企業の特徴
これらの視点を通して、あなたの会社にとって最適なWebマーケティング体制を構築するためのヒントを提供できれば幸いです。
なぜ今、Webマーケティングの「内製化」を検討する企業が増えているのか?
近年、多くの企業がWebマーケティングの内製化を検討しています。その背景には、いくつかの要因があります。
まず、市場環境の変化が挙げられます。新型コロナウイルスの流行以降、デジタルシフトが加速し、Webを活用した顧客接点や販促活動が不可欠となりました。これにより、Webマーケティングの重要性が増し、自社でコントロールしたいというニーズが高まっています。
また、コスト効率を重視する動きも強まっています。外注費用と比較し、長期的な視点で見れば内製の方がコストを抑えられる可能性があると考える企業が増えています。
さらに、変化への迅速な対応力、つまりスピードと柔軟性が求められる現代において、内製化は施策の実行や改善をスピーディに行えるというメリットがあります。
最後に、Webマーケティング活動を通じて得られるノウハウやデータを自社の資産として蓄積し、今後の事業成長に活かしたいという意識も高まっています。
これらの理由から、Webマーケティングの内製化は、企業の競争力強化のための重要な選択肢の一つとなっています。
市場環境の変化:デジタルシフトの加速と競争激化
近年、Webマーケティングを自社で行う「内製化」を検討する企業が増えています。その背景には、主に以下のような市場環境の変化があります。
-
デジタルシフトの加速:
-
特にコロナ禍以降、パソコンやスマートフォンを通じたインターネット利用時間が増加しました。
-
BtoCだけでなく、BtoBにおいても製品購入やサービス契約でWebを活用することが不可欠になっています。
-
-
競争激化:
-
多くの企業がWebを活用した情報発信や販促に乗り出しています。
-
インターネットを通じて全世界に一斉に情報を発信できるようになった反面、その中で自社の存在を際立たせるには、戦略的なWebマーケティングが求められています。
-
こうした状況下で、企業は顧客に自社の商品・サービスを効果的にアピールし、集客・販売促進につなげる必要性を強く認識しています。 Webマーケティングは、施策の効果を数値化しやすく、定量的なデータに基づいた改善を行いやすいという特徴から、この変化の速い市場で成果を出すための重要な手段となっています。
コスト効率の重視:外注費用と内製コストの比較検討
Webマーケティングの内製化を検討する企業が増えている背景には、コスト効率への意識の高まりがあります。
外注する場合、専門知識を持つ外部の力で迅速に成果を期待できますが、継続的な委託費用が発生します。一方、自社でWebマーケティングを行う場合、初期投資として担当者の人件費や育成費、ツール導入費用などがかかります。しかし、長期的に見れば、ノウハウやデータが社内に蓄積されることで、施策の最適化が進み、コスト削減につながる可能性があります。
特にSEOのように効果が出るまでに時間がかかる施策でも、社内リソースを活用することで、費用を抑えながら継続的に取り組める点がメリットです。
|
コストの種類 |
外注した場合 |
内製した場合 |
|
初期費用 |
契約金など |
担当者の人件費、育成費、ツール費用など |
|
ランニングコスト |
継続的な委託費 |
人件費、ツール利用料、情報収集コストなど |
|
長期的な視点 |
委託費が発生し続ける |
ノウハウ蓄積で効率化・コスト最適化の可能性 |
このように、内製化は短期的なコストだけでなく、長期的な視点でのコストメリットを考慮して検討されるケースが増えています。
スピードと柔軟性の追求:変化への迅速な対応力
Webマーケティングは、市場やユーザーのニーズが常に変化しています。特にデジタル化が進む現代では、トレンドの移り変わりも非常に速いです。
このような状況で成果を出し続けるには、
-
施策の効果をリアルタイムで把握し
-
分析結果に基づいた迅速な改善
-
新しい手法への挑戦
などが不可欠となります。
外注の場合、コミュニケーションや確認に時間がかかり、スピーディーな対応が難しいケースがあります。一方、自社内で運用していれば、意思決定から実行までがスムーズになり、変化に即座に対応しやすくなります。
例えば、Webサイトのアクセスデータを見て課題が見つかった場合、内製であればすぐにコンテンツの修正や広告クリエイティブの変更といったアクションに移れます。また、新しいSNSが登場した場合なども、社内のリソースで柔軟に検証・導入を検討できます。
このように、変化の速いWebマーケティングの世界では、自社でコントロールできる体制を築くことが、競争優位性を保つ上で重要な視点となります。
ノウハウの蓄積と資産化への意識向上
近年、Webマーケティングのノウハウを自社内に蓄積し、企業の資産として活用したいと考える企業が増えています。
Webマーケティングの大きな特徴の一つは、施策の効果を詳細に数値化できる点です。
-
Webマーケティングで数値化できる情報例
-
Webサイトへの訪問経路
-
サイト内でのユーザーの行動(どのページを見たか、どのくらいの時間滞在したかなど)
-
問い合わせや購入に至った経緯
-
これらのデータを継続的に分析することで、どのような施策が効果的か、顧客はどのようなニーズを持っているかといった貴重なノウハウが社内に蓄積されます。
このノウハウは、将来的なマーケティング戦略の立案や、新たな担当者への引き継ぎなど、長期的に企業の競争力強化に繋がる重要な資産となります。外注に頼りきりでは得られない、自社ならではの知見を培うことができるため、内製化への関心が高まっています。
Webマーケティングを自社で行うことのメリット・デメリット
Webマーケティングを自社で行う(内製化)ことには、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
内製化のメリット
-
自社ビジネスや顧客への理解が深まり、施策に反映しやすい
-
リアルタイムでの情報共有や意思決定が可能になり、変化に迅速に対応できる
-
施策のノウハウや蓄積されたデータが社内資産となる
-
長期的に見てコスト最適化の可能性がある
内製化のデメリット
-
専門知識やスキルを持つ人材の確保・育成に時間とコストがかかる
-
担当者のリソース不足により、業務が滞るリスクがある
-
特定の担当者に業務が集中し、属人化する可能性がある
-
Webマーケティングの最新情報を常にキャッチアップする体制が必要になる
内製化を検討する際は、これらのメリットとデメリットを十分に比較検討し、自社の体制や目指す方向性に合っているかを見極めることが重要です。
内製化のメリット:
Webマーケティングを自社で行うことには、多くのメリットがあります。まず、自社のビジネスや顧客ニーズに合わせて、より柔軟かつ迅速に施策を実行できる点が挙げられます。市場や顧客の反応をリアルタイムで把握し、即座に施策に反映させることが可能です。
また、施策の企画から実行、効果測定、改善までを一貫して社内で行うことで、Webマーケティングに関する貴重なノウハウやデータが社内に蓄積されます。これは将来的なマーケティング活動において重要な資産となります。
さらに、外部に委託する際に発生するコミュニケーションコストやマージンを削減できる可能性があり、長期的に見ればコスト効率の最適化につながることも期待できます。
|
メリット項目 |
具体的な利点 |
|
柔軟性とスピード |
自社に合わせた迅速な施策実行、リアルタイムな対応 |
|
ノウハウ・データ蓄積 |
施策ノウハウ、顧客データの社内資産化 |
|
コスト最適化 |
外部コスト削減による効率化の可能性 |
|
顧客理解の深化 |
顧客との直接的な接点増加 |
これらのメリットを享受することで、Webマーケティング活動を自社の成長に直結させることが可能になります。
自社に合わせた施策の柔軟な実行
Webマーケティングを自社で行う大きなメリットの一つは、変化する状況に合わせて施策を迅速かつ柔軟に調整できる点です。
例えば、自社の商品やサービスに対する顧客の反応が予想と異なった場合、外注先に依頼するよりも早く、社内で議論して施策内容を修正し、実行に移すことができます。また、競合他社の動きや市場トレンドの変化にも素早く対応し、新しい施策をすぐに試すことも可能です。
Webマーケティングの強みは施策の効果を数値で詳細に把握できることです。このデータをリアルタイムで社内共有し、即座に次のアクションに繋げられるのは内製化ならではのメリットと言えます。
これにより、PDCAサイクルを高速で回し、より効果的な施策へと改善していくことが容易になります。
リアルタイムな情報共有と意思決定
Webマーケティングを自社で行う大きなメリットの一つは、情報の共有と意思決定が迅速に行える点です。
外注の場合、代理店との間にコミュニケーションのタイムラグが発生したり、情報がスムーズに伝わりにくかったりすることがあります。しかし内製化していれば、担当部署間で直接的に情報交換が可能です。
例えば、
-
Webサイトのアクセス状況
-
広告運用の成果
-
SNSへのユーザー反応
といったデータをリアルタイムで把握し、その場で関係者と共有できます。これにより、市場や顧客の反応に対する理解が深まり、施策の微調整や改善、新たな戦略の立案といった意思決定をスピーディーに進めることができます。
特に変化の速いWeb業界においては、迅速な対応が成果に直結するため、このリアルタイム性が内製化の大きな強みとなります。
施策ノウハウ・データの社内蓄積
Webマーケティングを自社で行う大きなメリットの一つは、施策から得られるノウハウやデータを社内に蓄積できる点です。外注の場合、運用レポートや分析結果は共有されますが、具体的な運用手法や試行錯誤の過程で得られた知見は、サービスを提供する会社側に溜まっていくことが多いです。
一方、内製化では、日々の運用データ(例:Webサイトへのアクセス経路、ユーザーの行動、コンバージョンに至るまでの流れなど)が全て自社に蓄積されます。Webマーケティングは「定量的効果測定をもとにした施策の改善を行いやすい」という特徴があります。このデータを基に、
-
どのような施策が効果的だったか
-
どのようなユーザー層に響いたか
-
改善点は何か
といった分析を繰り返し行うことで、具体的な成功・失敗事例、自社ならではの知見が社内共有されます。これにより、担当者が替わっても継続的に改善を進められる体制が構築でき、企業のマーケティング資産として活用できるようになります。
コスト最適化の可能性
Webマーケティングを自社で行うことのメリットの一つに、コスト最適化の可能性が挙げられます。
外注の場合、一般的に広告運用費に加えて代行手数料が発生します。この手数料は運用費の〇〇%という形で設定されることが多く、運用額が増えるほど手数料も増加します。
一方、内製化であれば、担当者の人件費やツールの利用料、広告費などの実費が主なコストとなります。初期投資や担当者の育成費用はかかりますが、長期的に見れば手数料部分を削減できる可能性があります。
特に、広告運用費が大きい場合や、複数の施策を継続的に行う場合、内製化によるコスト削減効果が大きくなる傾向があります。
|
コスト項目 |
外注の場合 |
内製の場合 |
|
広告運用費 |
実費 |
実費 |
|
代行手数料 |
発生 |
発生しない |
|
人件費 |
外注先へ支払い |
自社で負担 |
|
ツール利用料 |
外注先が負担 or 自社負担 |
自社で負担 |
|
初期投資 |
少なめ |
必要 (育成・環境) |
ただし、内製化によるコスト最適化を実現するには、効率的な運用体制の構築や、担当者のスキルアップが不可欠です。
顧客理解の深化
Webマーケティングを内製化することで、顧客理解をより深めることができます。外注の場合、顧客データや施策の反応はベンダーを介して得られることが多いですが、自社で直接運用することで、リアルタイムに多様な顧客情報に触れる機会が増えます。
例えば、Webサイト上でのユーザーの行動データ(どのページを見たか、どれくらいの時間滞在したか、どこから流入したかなど)や、広告に対する反応、SNSでのエンゲージメントなどを直接分析できます。これにより、顧客がどのような情報に関心を持ち、どのような課題を抱えているのかを肌で感じることができます。
-
具体的な顧客理解の深め方
-
行動データの分析: Webサイトのアクセス解析からユーザーの興味関心を把握
-
施策への反応: 広告クリック率やコンテンツの閲覧状況からニーズを推測
-
直接的なコミュニケーション: SNSや問い合わせフォームからの声に耳を傾ける
-
これらの一次情報を直接分析し、社内で共有することで、顧客像(ペルソナ)や購買プロセス(カスタマージャーニー)への理解が深まります。これは、より顧客の心に響くコンテンツ作成や、効果的な施策立案につながり、結果として顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上に貢献します。
内製化のデメリット:
Webマーケティングを自社で行うことは多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。
まず、専門知識やスキルの習得、そして最新情報のキャッチアップには時間とコストがかかります。特に初期段階では、担当者の育成に加えて、効果測定や分析に必要なツールへの投資も必要になる場合があります。
また、内製化は担当者に業務が集中しやすく、リソース不足による遅延や業務過多のリスクが伴います。担当者が不在になった場合、業務が滞る「属人化」のリスクも高まります。
これらのデメリットを理解し、対策を講じることが、内製化を成功させる鍵となります。
専門知識・スキルの習得と維持コスト
Webマーケティングを内製化する上で、専門知識やスキルの習得は避けて通れません。特に、経験がない担当者を育成するには時間とコストがかかります。実践レベルに達するためには、専門的な講座やスクールでの学習が効果的ですが、これには費用が発生します。
スクールの費用は20万円から60万円程度が相場とされています。また、最新の知識やトレンドを常にキャッチアップし続けるための学習コストも継続的に必要になります。社内だけで情報収集を行うには限界があるため、外部セミナーへの参加や専門資料の購読なども視野に入れる必要があります。
初期投資として人材育成に費用がかかるだけでなく、常に変化するWebマーケティングの知識をアップデートしていくための継続的なコストと労力が必要となる点が、内製化のデメリットと言えます。
担当者の育成時間と初期費用
Webマーケティングを内製化する際には、専門知識やスキルを持った担当者を育成する必要があります。これには、時間とコストがかかります。
SEOやWeb広告運用、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングなど、Webマーケティングには多岐にわたる施策があります。それぞれの施策には専門的な知識や運用スキルが求められます。
例えば、
-
SEO: アルゴリズム理解、コンテンツ最適化、テクニカルSEOなど
-
Web広告: 各媒体の仕組み、ターゲティング設定、予算管理、効果測定など
-
コンテンツマーケティング: 企画、ライティング、編集、配信チャネル選定など
これらのスキルをゼロから習得するには、研修費用や学習時間が必要です。また、効果測定や分析のためのツールの導入費用なども初期コストとして発生します。担当者がスキルを習得し、実際に成果を出せるようになるまでには、ある程度の期間を見込む必要があるでしょう。
リソース不足による業務過多・遅延リスク
Webマーケティングを内製化する際のデメリットの一つとして、社内リソースの不足が挙げられます。
Webマーケティングには、多様な施策と専門的なスキルが求められます。例えば、
-
SEO(検索エンジン最適化)
-
Webサイトの運営・改善
-
リスティング広告やSNS広告などの広告運用
-
SNSマーケティング
-
動画マーケティング
-
コンテンツマーケティング
など、幅広い業務が存在します。
これらの施策を自社ですべて行おうとすると、既存の業務に加え、新たな専門スキルを持った担当者が必要です。人材が不足している場合、一人あたりの業務量が増加し、業務過多に陥る可能性があります。これにより、各施策の実行が遅れたり、質が低下したりするリスクが生じます。
また、Webマーケティングは効果測定と改善を継続的に行う必要がありますが、リソースが限られていると、分析や改善に十分な時間を割けず、成果が出にくくなることも考えられます。
担当者不在時の属人化リスク
Webマーケティングを自社で行う場合、特定の担当者に業務やノウハウが集中し、「属人化」するリスクがあります。これは、担当者が異動したり退職したりした場合に、それまで蓄積された知識や運用方法が失われ、業務が滞る可能性があることを指します。
特に、SEO対策や広告運用、SNS運用など、専門的な知識や継続的なデータ分析が必要な施策では、属人化が起こりやすい傾向にあります。
例えば、
-
SEO担当者: 検索エンジンのアルゴリズム変動への対応方法や、サイト改善のノウハウが共有されていない。
-
広告運用担当者: 過去の運用データや成功・失敗事例が担当者のPC内にしかない。
-
SNS担当者: 炎上対策やコミュニティ形成のノウハウが言語化されていない。
このような状態では、担当者が不在になった際に、ゼロから体制を立て直す必要が生じ、時間とコストがかかります。属人化を防ぐためには、マニュアル作成や定期的な情報共有、複数担当制の導入などが重要になります。
最新情報のキャッチアップ体制の構築
Webマーケティングの世界は常に変化しており、最新の知識やトレンドを把握し続けることが重要です。SEOのアルゴリズム変更、新しい広告プラットフォームの登場、SNSの機能アップデートなど、情報は日々更新されています。
内製でWebマーケティングを行う場合、これらの最新情報を自社で積極的に収集し、学び続ける体制を構築する必要があります。これは、担当者が個人的に行うだけでなく、企業として情報収集や学習の機会を提供することが望ましいです。
具体的には、以下のような方法が考えられます。
-
専門メディアやブログの購読:Webマーケティングに関する最新情報を発信する専門メディアや業界ブログを定期的にチェックします。
-
セミナーやウェビナーへの参加:最新のノウハウや成功事例を学ぶために、セミナーやウェビナーに積極的に参加します。
-
オンライン学習プラットフォームの活用:体系的に知識を習得するために、UdemyやCourseraなどのオンライン学習プラットフォームを利用します。
-
業界コミュニティへの参加:他の企業担当者との情報交換を通じて、実践的な知見を得ます。
特にWeb広告やSNS広告などは、媒体ごとの特性や最新のアルゴリズムを理解しているかが成果に直結するため、継続的な学習が不可欠です。
このような体制が整っていないと、古い知識に基づいた施策を実行してしまい、期待する効果が得られないリスクが高まります。内製化を成功させるためには、継続的な学習と最新情報のキャッチアップを仕組み化することが非常に重要と言えます。
Webマーケティングを内製化するための具体的なステップ
Webマーケティングを自社で行うには、計画的に進めることが重要です。以下のステップで着実に導入を進めましょう。
-
目的・目標の明確化: 何のためにWebマーケティングを行うのか(例: 認知拡大、リード獲得、売上向上など)を具体的に設定します。数値目標(KGI)も定めましょう。
-
ターゲット設定: どのような顧客にアプローチしたいのか、詳細なペルソナを設定し、顧客の行動プロセス(カスタマージャーニー)を理解します。
-
施策範囲の決定: 内製化するWebマーケティング施策を具体的に選びます。SEO、Web広告、SNS、コンテンツマーケティングなど、様々な手法があります。自社の目的やリソースに合わせて優先順位をつけましょう。
-
体制構築とリソース確保: 必要な専門知識を持つ人材、運用ツール、そして予算を確保します。専任チームを作るのか、既存社員が兼任するのかなど、体制を構築します。
-
計画・実行: 選定した施策の具体的な実行計画を立て、実施します。
-
効果測定と分析: 設定したKPIに基づき、施策の効果を測定します。データ分析ツールなどを活用し、成果を詳細に把握します。
-
改善: 分析結果をもとに、課題を見つけ、施策を改善します(PDCAサイクル)。
-
ノウハウ共有: 施策の成果や学びを社内で共有し、ナレッジとして蓄積する仕組みを作ります。
これらのステップを踏むことで、効果的な内製化を目指せます。
Step1:目的・目標(KGI)の明確化と現状分析
Webマーケティングを内製化する最初のステップは、何のために内製化するのか、どのような成果を目指すのかを明確にすることです。
具体的には、
-
最終的な目標(KGI)の設定:
-
売上〇〇円増加
-
問い合わせ数〇〇件達成
-
ブランド認知度〇〇%向上 など、具体的な数値目標を設定します。
-
-
現状分析:
-
現在のWebサイトへのアクセス状況
-
既存のマーケティング施策の効果
-
競合他社の動向 などを分析し、目標達成に向けた課題を洗い出します。
-
このステップは、その後の施策の方向性を決定し、効果測定の基準となるため非常に重要です。Webマーケティングは効果を数値化しやすいという特徴があるため、初期段階での目標設定と現状分析が、成功への鍵となります。
Step2:ターゲット顧客(ペルソナ)とカスタマージャーニーの設定
Webマーケティングを内製化する上で、誰に情報を届けたいのかを明確にすることが非常に重要です。
まず、「ペルソナ」を設定しましょう。ペルソナとは、自社の理想的な顧客像を具体的に設定したものです。年齢、性別、職業、居住地、趣味、価値観、悩みなどを詳細に定義することで、ターゲット顧客を深く理解できます。
次に、そのペルソナが商品やサービスを知ってから購入・契約に至るまでの道のり、「カスタマージャーニー」を可視化します。
|
段階 |
顧客の行動例 |
自社が行うべき施策例 |
|
認知 |
課題に気づく、情報収集を開始する |
SEO、Web広告、SNS発信 |
|
興味・関心 |
特定の製品・サービスに興味を持つ |
コンテンツマーケティング(ブログ、動画) |
|
比較・検討 |
複数の選択肢を比較する |
事例紹介、製品詳細ページ、資料請求 |
|
購入・契約 |
意思決定し、購入・契約に進む |
LP最適化、EFO(入力フォーム最適化) |
|
利用・推奨 |
製品・サービスを利用し、評価する |
メルマガ、SNSでの交流、レビュー促進 |
このように、ペルソナの各段階の行動や心理を理解することで、どの段階でどのようなWebマーケティング施策が効果的かが見えてきます。これにより、やみくもに施策を行うのではなく、顧客に寄り添った効率的なマーケティングが可能になります。
Step3:内製化する施策範囲の決定(例:SEO、広告運用、SNS、コンテンツ作成など)
Webマーケティングには、集客、接客、販売促進の段階に応じた様々な施策があります。すべてを一度に内製化するのは難しいため、自社の目的やリソースに合わせて、優先的に取り組む施策範囲を決定することが重要です。
代表的な施策として以下の種類が挙げられています。
-
集客施策
-
SEO(検索エンジン最適化)
-
Web広告(リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など)
-
SNSマーケティング
-
コンテンツマーケティング
-
動画マーケティング
-
-
接客・販売促進施策
-
Webサイト運営(コンテンツ更新、分析・改善など)
-
例えば、即効性を求めるならWeb広告、長期的な資産として取り組むならSEOやコンテンツマーケティングなどが考えられます。自社の強みや弱み、目標とするKGI・KPI達成に最も貢献する施策を選びましょう。
Step4:必要な人材・ツール・予算の確保と体制構築
Webマーケティングの内製化を進める上で、最も重要なステップの一つが、必要なリソースの確保と体制構築です。
まず、誰がどのような役割を担うのか、具体的な担当者を決めましょう。SEO担当者、広告運用担当者、コンテンツマーケティング担当者など、施策範囲に応じて必要な専門スキルを持つ人材が必要です。社内に適任者がいない場合は、採用や育成を検討します。
次に、施策実行に必要なツールを選定し、導入します。例えば、SEO効果測定ツール、広告運用管理ツール、アクセス解析ツール(Google Analyticsなど)、SNS管理ツールなどです。
そして、これらの人材とツールにかかる予算を確保します。初期投資だけでなく、継続的な運用費用も考慮に入れる必要があります。
最後に、これらの要素を組み合わせて、スムーズにWebマーケティング活動を進められる体制を構築します。情報共有のルール、効果測定の報告体制などを明確にすることが成功の鍵となります。
Step5:選定した施策の計画・実行
内製化するWebマーケティング施策の範囲が決まったら、いよいよ具体的な計画を立て実行に移します。計画の際には、目標達成に向けた具体的なアクションプラン、スケジュール、担当者を明確にすることが重要です。
計画・実行する施策例としては、以下のようなものがあります。
-
SEO(検索エンジン最適化): 検索順位上昇を目指したコンテンツ作成やサイト改善を行います。効果が出るまで時間がかかる傾向があります。
-
Web広告: リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など、ターゲットに合わせた広告媒体を選定し、予算内で運用します。即効性が期待できる一方、運用スキルが必要です。
-
SNSマーケティング: 企業の公式アカウントを運用し、情報発信やユーザーとのコミュニケーションを通じて認知拡大やエンゲージメント向上を図ります。
-
コンテンツマーケティング: ブログ記事、動画、ホワイトペーパーなど、ターゲットにとって価値のあるコンテンツを作成・配信し、潜在顧客の獲得や育成を目指します。
これらの施策は、集客、接客、販売促進といったマーケティングの各段階で役割が異なります。自社の目的やリソースに合わせて、最適な施策を組み合わせて実行することが成功の鍵となります。
Step6:効果測定(KPI設定)とデータ分析
Webマーケティング施策は実行して終わりではありません。設定した目標(KGI)達成に向けた中間指標であるKPIを設定し、必ず効果測定とデータ分析を行いましょう。
Webマーケティングの大きな特徴は、施策の効果を数値化できる点です。たとえば、Webサイトへのアクセス数、ユーザーのサイト内での行動、コンバージョン数などを詳細に追跡できます。
データ分析を通じて、以下の点を把握します。
-
施策が目標達成にどれだけ貢献しているか
-
どの施策が効果的で、どの施策に課題があるか
-
ユーザーはどのような行動をとっているか
これらの数値データを分析することで、客観的な根拠に基づいた改善策を見つけ出すことができます。
主な効果測定の例:
|
施策の種類 |
主なKPI例 |
|
SEO |
検索順位、オーガニック流入数、コンバージョン率 |
|
Web広告 |
クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、獲得単価(CPA) |
|
SNSマーケティング |
エンゲージメント率、フォロワー増加数、サイト流入数 |
正確な効果測定とデータ分析が、次の改善ステップにつながる重要な工程です。
Step7:分析結果に基づく施策の改善(PDCAサイクル)
施策を実行したら、必ず効果測定を行い、その結果に基づいて改善を続けることが重要です。Webマーケティングの大きな特徴は、その効果を数値化できる点にあります。
-
数値化できるデータ例
-
Webサイトへのアクセス数
-
ユーザーのサイト内での行動(滞在時間、ページ遷移など)
-
問い合わせ数や購入数(コンバージョン率)
-
広告のクリック率や費用対効果
-
これらのデータを分析することで、何がうまくいき、何が課題なのかを具体的に把握できます。例えば、広告からの流入は多いがコンバージョンが低い場合、LP(ランディングページ)に問題があるかもしれません。SEOでアクセスが増えない場合は、キーワード選定やコンテンツの内容を見直す必要があるでしょう。
分析結果をもとに、施策のどこを改善するか計画を立て、実行に移します。そして再度効果測定を行う、この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを継続的に回すことで、施策の効果を最大化し、内製化の精度を高めていくことができます。
Step8:ノウハウの共有と仕組み化
Webマーケティングを内製化する上で非常に重要なステップが、獲得したノウハウを組織全体で共有し、仕組み化することです。これは、担当者が不在になった際の属人化リスクを防ぎ、継続的に成果を出すための土台となります。
具体的な取り組みとしては、以下のような方法があります。
-
議事録やレポートの作成・共有: 会議や施策の結果を文書化し、関係者がいつでも確認できるようにします。
-
社内勉強会や研修の実施: 成功事例や失敗事例、最新のトレンドなどを共有し、チーム全体のスキルアップを図ります。
-
ツールの活用: プロジェクト管理ツールや情報共有ツールなどを活用し、情報の一元化とアクセス性を高めます。
-
標準プロセス・マニュアルの作成: 定型的な業務フローや手順をマニュアル化し、誰でも同じ品質で業務を行えるようにします。
これらの取り組みを通じて、個人の知識や経験を組織の資産に変え、安定した運用体制を築くことができます。
あなたの会社は内製化に向いている?適性を見極める3つの判断ポイント
Webマーケティングの内製化が自社に適しているかどうかを見極めるには、いくつかの重要な視点があります。闇雲に始めるのではなく、以下の3つのポイントで慎重に判断することが成功への鍵となります。
まず一つ目は、社内にWebマーケティングに対する「理解」と施策を推進していく「推進力」があるかです。経営層から現場まで、Webマーケティングの重要性を理解し、前向きに取り組む姿勢が不可欠です。
二つ目は、内製化に必要な「人材」と「予算」を確保できるかという点です。専門知識を持つ人材の採用・育成や、必要なツール導入、広告費などの予算を継続的に投下できるかを確認しましょう。SEOなどはコストを抑えられますが手間がかかり、動画マーケティングはコストがかかる傾向にあります。施策によって必要なリソースは異なります。
三つ目は、変化に迅速に対応できる「スピード感」を重視するかどうかです。内製化であれば、市場や顧客の反応に素早く対応し、施策を柔軟に改善していくことが可能です。このスピード感を組織として持てるかが問われます。
これらのポイントを総合的に判断し、自社の状況に合った体制を検討することが重要です。
ポイント1:社内にWebマーケティングへの「理解」と「推進力」があるか?
Webマーケティングの内製化を検討する際、まず確認したいのが、社内にWebマーケティングそのものへの理解があるか、そして推進していくための熱意や体制があるかという点です。
Webマーケティングは、一度取り組めば終わりではなく、効果測定と改善を繰り返す継続的な活動です。そのため、経営層から現場担当者まで、施策の目的や効果が出るまでの期間などを正しく理解している必要があります。
特に、効果が出るまでに時間がかかるSEOやコンテンツマーケティングなどは、短期的な成果を求めすぎず、中長期的な視点で取り組むことへの理解が不可欠です。
また、施策を実行し、PDCAサイクルを回していくためには、担当者だけでなく、関連部署との連携や、新しい知識・スキルを学ぶための環境整備なども重要になります。社内全体で内製化を「自分たちのこと」として捉え、前向きに進めていく推進力がなければ、途中で頓挫してしまうリスクが高まります。
内製化を成功させるためには、単に担当者を置くだけでなく、社内全体の意識と体制が整っているかどうかが重要な判断ポイントとなります。
ポイント2:内製化に必要な「人材」と「予算」を確保できるか?
Webマーケティングの内製化を検討する上で、無視できないのが「人材」と「予算」の確保です。
内製化には、専門知識やスキルを持つ人材が不可欠です。例えば、SEO、広告運用、SNS、コンテンツ作成など、施策の種類によって必要なスキルは異なります。SEOは「社内のリソースを使ってコストを抑えながら取り組める点がメリットですが、その分、手間や工数がかかる点と効果が出るまでに時間がかかることがデメリット」とされており、継続的な人員配置が必要です。
また、Web広告など、施策によっては初期費用や運用コストがかかります。Web広告の種類を見ても、それぞれに最低限必要な予算が運用方針によって異なると説明されています。
内製化を進めるには、これらの人的・金銭的コストを事前に見積もり、社内で確保できるか、または育成・投資する体制を整えられるかを検討する必要があります。
|
内製化に必要な要素 |
確認ポイント |
|
人材 |
専門知識・スキルを持つ担当者はいるか? 育成計画は? |
|
予算 |
初期費用・運用コストを確保できるか? |
ポイント3:変化に迅速に対応できる「スピード感」を重視するか?
Webマーケティングの世界は常に変化しています。新しい手法が登場したり、アルゴリズムが更新されたりするため、市場や顧客の動きに合わせて迅速に施策を変更・実行できる体制が重要になります。
内製化の大きなメリットの一つは、この「スピード感」にあります。例えば、
-
リアルタイムな情報共有と意思決定: 市場の変化や効果測定の結果をすぐに社内で共有し、次のアクションを迅速に決定できます。
-
自社に合わせた施策の柔軟な実行: 外部との調整にかかる時間を省き、状況に応じて施策内容や予算配分を柔軟に変更できます。
Webマーケティングでは施策の効果測定を数値で行い、そのデータに基づいて改善を行うことが重要です。内製であれば、このPDCAサイクルを素早く回し、競合よりも早く変化に対応することが可能になります。
ただし、迅速な対応には、担当者のスキルや判断力も不可欠です。体制構築の際には、担当者が自律的に動ける環境を整えることも考慮しましょう。
【文字数確認】 上記の本文は、句読点等含め379文字です。指定された400文字程度に収まっています。
失敗しないためのチェックリスト
内製化の適性を見極めるためのチェックリストとして、以下の3つのポイントを確認してみましょう。
|
チェックポイント |
確認内容 |
|
1. Webマーケティングへの理解と推進力 |
経営層や関係部署がWebマーケティングの重要性を理解し、推進体制を構築できるか? |
|
2. 人材と予算の確保 |
専門知識を持つ人材を採用・育成し、必要なツールや広告費などの予算を確保できるか? |
|
3. スピード感 |
市場の変化や施策の効果測定結果に基づいて、迅速に改善を実行できる組織体制か? |
これらのポイントをクリアできれば、内製化は成功しやすいと言えます。逆に、これらが難しい場合は、まずは一部施策の外注やハイブリッド体制から始めることも検討しましょう。
内製化と外注のハイブリッドという選択肢
Webマーケティングの内製化と外注は、どちらか一方を選ぶだけでなく、両者を組み合わせる「ハイブリッド」という選択肢も有効です。
例えば、専門性の高い領域や、ノウハウが社内にない施策(高度なSEO対策、複雑な広告運用など)は外部の専門業者に依頼し、日常的な運用やコンテンツ作成、顧客とのコミュニケーションといった部分は自社で行うといった方法があります。
このアプローチのメリットは、以下の通りです。
-
専門性の活用: 外部の知見を活用し、効率的に成果を追求できます。
-
リソースの補完: 社内リソースが不足している部分を外注で補えます。
-
ノウハウの共有: 外注先から専門知識を学び、社内に蓄積することも可能です。
-
コスト効率: 全てを内製するよりも、初期投資や専門人材育成コストを抑えられる場合があります。
特に、内製化を始めたばかりで不安がある場合や、特定の施策で早期に成果を出したい場合に適しています。自社の現状や目標に合わせて、内製と外注の最適なバランスを見つけることが重要です。
まとめ:自社に最適なWebマーケティング体制を構築するために
Webマーケティングの内製化か外注かの判断は、企業の状況によって異なります。重要なのは、自社の目的、リソース、スピード感を総合的に考慮し、最適な体制を構築することです。
内製化は、ノウハウ蓄積や迅速な対応が可能になる一方、専門知識やリソース確保が課題となります。 外注は、専門家の知見を活用できる反面、コストやコミュニケーションが重要です。
近年では、内製と外注の「ハイブリッド」という選択肢も増えています。例えば、戦略立案や一部の専門性の高い施策は外注し、日常的な運用やコンテンツ作成は内製で行うなど、柔軟な組み合わせが可能です。
最適な体制を選ぶためには、以下の点を自社内で十分に検討することが推奨されます。
-
目的・目標: Webマーケティングで何を達成したいのか?
-
現状のリソース: 予算、人員、スキルはどの程度か?
-
優先順位: スピード、コスト、ノウハウ蓄積、どれを重視するか?
これらの要素を踏まえ、自社に合った体制を構築することで、Webマーケティングの効果を最大化し、事業成長につなげることができるでしょう。
